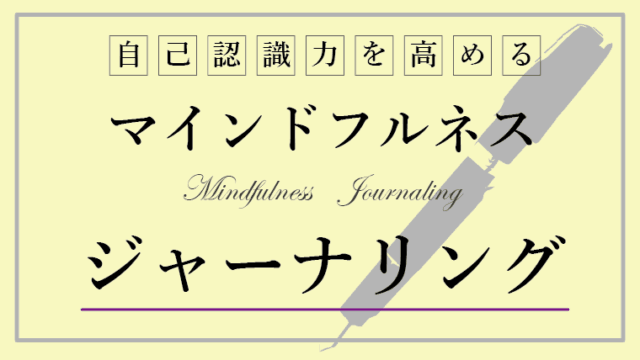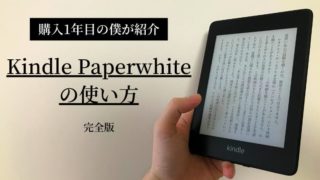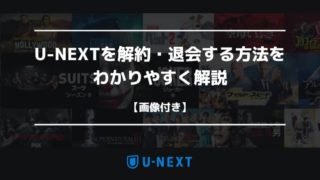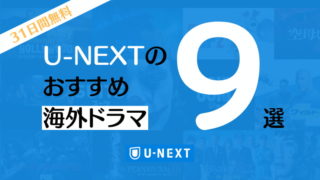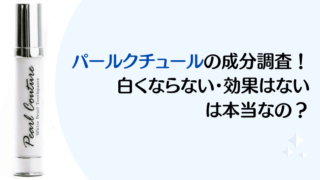PDCAサイクルをしっかり回せていますか?
PDCAサイクルは、Plan(計画)- Do(実行)- Check(評価)- Act(改善)の4つのプロセスを通して、設定した目標に向かって改善するためのフレームワークです。
目標に向かって進むためには、このPDCAサイクルに沿って進めることが効果的です。
しかし周りを見回しても、PDCAサイクルがうまく機能していないことが多いので、今回の記事ではPDCAサイクルをしっかりと機能させて、効果を出す方法をご紹介します。
ちなみに僕は、会社で部門内における生産管理を役割として担当しています。生産管理では生産性の維持ももちろん必要ですが、生産性の改善が重要なポイントになります。
年度目標を立てて、PDCAサイクルのフレームワークを使って改善を推進していますが、僕の部門では年度末を待たずに目標を達成、目標値を上げてはまた達成、と他部門と比較してもずば抜けて成果を上げています。(別に目標が低いわけじゃないですよ)
今回ご紹介するのは、こんな僕が実践しているPDCAサイクルです。
PDCAサイクルは小さいほど成果が上げやすい

なんやねん、小さいって。。
という声が聞こえてきそうですが、ここからしっかり解説していきます。
目標を立てたら、何でもかんでもPDCAサイクルに沿って進めればよいわけではありません。設定した目標って、ちょっとしたことで達成できるような簡単な内容ではないですよね。言わば、大きな目標なわけです。
大きな目標に対して、設定するPDCAサイクルは大きなPDCAサイクルということになります。PDCAサイクルがうまく機能していない人は、この大きなPDCAサイクルを回そうとしていることが原因です。
どういうことかと言うと、大きなPDCAサイクルになると具体性のない計画となってしまい、実施しても、うまく評価できないため、改善することもできず、成果が上がらず、PDCAサイクルが機能しないということです。
これに対して、小さなPDCAサイクルは、
- 計画が具体的になる
- 実施する内容が明確でブレない
- 評価が容易に行える
- 結果から改善点を見出しやすい
というメリットがあります。
小さいPDCAサイクルを回すための手順
小さなPDCAサイクルを回すための手順は以下のとおりです。
- 現状把握と目標とのギャップ(=課題)を知る
- 課題を分解する
- 課題ごとにPDCAサイクルを回す
現状把握と目標とのギャップ(=課題)を知る
目標を設定したら、第一に自分自身の現状把握を行います。現状を把握し、目標との正確なギャップを知ることから始めます。
ギャップとは、すなわち目標までの道のりにある課題です。現状把握をしっかりと行わなければ、目標にたどり着くまでに向かう道のりを見誤ってしまいます。そういう意味では一番重要なポイントと言えます。
このとき、できる限り客観的に自分を見つめるようにしてください。自分を背伸びさせないこと、また過小評価しないことを心がけます。今の自分は「何ができて、なにができないか」を具体的にしておきましょう。
課題を分解する
目標にたどり着くまでの課題はひとつではありません。目指す目標によって、課題を複数に分解できます。
TOEICテスト○○点を例として僕なりに課題の分解を考えてみました。ちなみにTOEICテストは、英語のリスニング・リーディングの能力を測定するテストです。
■勉強時間の確保
■語彙力(単語・熟語)
■読解力(文法・語法)
■リスニング力
■リーディング力
■TOEICテスト傾向
■TOEICテスト攻略(時間対策)
各項目でさらに細分化することはできますが、一段階小さくするとしたら、こんなところでしょうか。
よくあるのは課題をひっくるめて、とてつもなく大きなモノと勘違いしてしまうことです。よくよく分析してみると、小さな課題がいくつも重なっていることが多いです。ひとつひとつ着実に課題をクリアすることで目標達成に近づけます。
次に課題を難易度の低いもの、または基礎となるものから順番に並べます。並んだ順番がこれから上っていく階段です。その階段の一段が小さな目標だと考えてください。課題が解決したら小さな目標の達成です。小さな目標を達成して最終的には大きな目標を達成に繋げます。
小さな目標の設定の仕方について。
例えば、TOEICテストの目標点数によっては、文法は基本であったとしても、覚えておくべき単語数などが変わってくると思います。自分の目指す点数に合わせて「頻出単語1000語を覚える!」など、小さな目標を設定してください。
課題ごとにPDCAサイクルを回す
後は、小さな課題(=小さな目標)ごとにPDCAサイクルを回していきます。これが小さなPDCAサイクルです。
粒度が小さくなるから、以下のメリットが生まれます。
- 計画が具体的になる
- 実施する内容が明確でブレない
- 評価が容易に行える
- 結果から改善点を見出しやすい
【例】
目標:
頻出単語1000語を覚える!
Plan:
Input → 毎朝7時から30分間、TOEIC頻出単語集をチェック。
Output → ノートに書きだす。スキマ時間はアプリで復習。
Do:
Plan通りに実施。
Check:
毎週土曜日8時からTOEIC頻出単語集に沿って、覚えているかチェック。
Act:
覚えられていない単語に対してのどのようにしたら覚えられるか検討する。
いかがですか。わかりやすくなったでしょう。
たくさんの小さなPDCAサイクルをひとつずつ着実に回転させ小さな目標を達成することで、大きな目標の達成に繋がります。
ここで注意すべきポイントは、まとめて全部のPDCAを回すのではなく、1~3個程度の少ない数で回転させることです。どれもこれもが中途半端になってしまって、成果が伴わない結果になってしまうことがあるからです。そもそも人はマルチタスクに行動できるようになっていませんので、なるべくシングルタスクを心がけてください。
内容によっては、同時に進めた方が、理解度が高まるものもあると思います(語彙力と読解力のように)。ですので、何でもかんでもシングルタスクと考えずに効果も考えながら実施してください。
まとめ
おさらいですが、「PDCAサイクルは小さいほど効果は出やすい」です。
小さいPDCAサイクルを回すための手順は以下のとおり。
- 現状把握と目標とのギャップ(=課題)を知る
- 課題を分解する
- 課題ごとにPDCAサイクルを回す
僕自身、小さなPDCAサイクルを回すことで、大きな成果を上げることができています。
ぜひあなたも、小さなPDCAサイクルを実践して、大きな成果を上げてください。